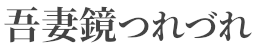源平争乱期、信濃源氏は木曽義仲の挙兵に呼応し、井上光盛は横田河原の合戦で平家方の越後国城氏を撃退した主力となるなど、同門ながら頼朝とは一定の距離をとって活動しました。では、どのようなきっかけで小坂光頼は鎌倉殿に仕えるようになったのでしょうか。そこには二代将軍頼家と、義父である比企能員の存在が浮かび上がります。
かつて頼朝に乳母として仕えた比企尼は、平治の乱で捕らわれ十二歳で伊豆国へ流罪となった頼朝の身を案じ、夫の掃部允と共に武蔵国比企郡へ移り住み、挙兵までの二十年間、物心両面で援助しました。頼朝が流刑地に来た当初、地元の者は平家の威光を憚り、誰ひとり食料すら与えなかったと言いますから、比企尼の支援は文字どおり命をつなぐ糧でした。
その恩に報いるため、頼朝は比企尼の養子だった能員を家臣に取り立て、厚い信頼を寄せました。なにしろ御台所政子が産気づくと、能員の屋敷(現在の比企谷に建つ妙本寺のあたり)を産所に定め、男児(後の頼家)が生まれると乳母夫(養父の意)に任じたほどです。長じた後、頼家は能員の娘若狭局を妻とし嫡子一幡をもうけます。能員は次代将軍の舅となり幕府内で強い権力を手に入れました。もし一幡が三代将軍となれば、北条家に取って代わり外祖父の地位を得るでしょう。

建久十年(一一九九年)二月、頼家は亡父の遺跡を相続して二代鎌倉殿となりますが、わずか二か月後に頼家の訴訟裁決権は剥奪され、北条時政をはじめとした十三人の重臣による合議制が導入されます。数え年で十八歳の若輩者に過ぎない頼家に、頼朝時代から仕えるくせ者ぞろいの御家人たちをまとめ上げる器量や求心力は望むべくもありません。
父頼朝は二十年に及ぶ流人生活の中で、坂東武者たちが一所懸命に所領経営に励む姿を間近に見てきましたから、いざ挙兵を遂げたときには、彼らが武家の棟梁に何を望むか、どうしたら彼らを服従させられるか、よく知り抜いていました。一方で、大蔵御所に住み武将らが鎌倉殿に平伏する姿を見て育ったお坊ちゃん将軍に、複雑な利害の絡まる御家人同士の泥々した相論をそつなく裁く能力はないと判断されたのでしょう。
その八日後、重臣たちの決定に当てつけるかのように、頼家は自分に忠誠を誓う側近五人衆、すなわち小笠原弥太郎長経、比企三郎宗朝、同弥四郎時員、中野五郎能成、和田三郎朝盛(細野四郎兵衛尉とも)が鎌倉内で狼藉を働いても衆人は敵対してはならぬと、かなり無茶な布告を政所に提出し、不満の意を表明します。また、この五人以外はたやすく御前に参上するなとも求めました。お前たちの顔など見たくない、というわけです。
ここで注目すべきは、側近五人衆のうち二人ないし三人が信濃出身者で固められたこと。小笠原長経は、文治元年(一一八五年)八月に頼朝の推挙により信濃守となった甲斐源氏加賀美遠光の孫です。父長清は伊奈郡伴野荘の地頭となり、承久の乱では東山道の主力部隊として参戦するなど、信濃武士として長く活動します。中野能成は高井郡中野郷を名字とする武士。細野四郎兵衛尉は安曇郡細野郷の武士と考えられます。頼朝時代には影の薄かった信濃武士は、幕府内で幅を利かせる北条、三浦、安達、畠山などとは一線を画す存在であり、それゆえ頼家は彼らを抜擢し親衛隊のように扱うことで重臣たちに対抗したかったのでしょう。
頼朝は源氏同門の武将を強く警戒し、佐竹秀義、志田義広、木曽義仲、源行家、一条忠頼、安田義定、さらに実弟の義経や範頼まで次々と粛清し、信濃源氏嫡流の井上光盛も一条忠頼に通じていたとして元暦六年に誅殺しました。一方で頼朝は、誅殺した武将の家人でも有能な者は幕府体制に取り込もうとする面もあり、井上光盛の侍だった保科太郎、小河原雲藤三郎を御家人に取り立てました。また信濃善光寺の再建に向け信濃国目代と荘園公領の沙汰人に対し造営に尽力するよう命じ、自身も善光寺参詣を計画するなど、信濃国を重視する姿勢を見せます。腹心の比企能員を同国の守護兼目代に任命したことにも、信濃武士を取り込もうとする政治的意図をくみ取れます。
(公開日:2025-08-07)