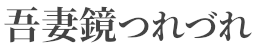鎌倉の地に武家政権を樹立した源頼朝は、文治五年(一一八九年)に奥州藤原氏を滅ぼして日本国内の対抗勢力を一掃します。翌建久元年(一一九〇年)には伊豆に配流されて以降初めて上洛し、後白河法皇をはじめとした朝廷重鎮たちと相次いで面談して武家政権と朝廷の融和を進めます。そして建久三年(一一九二年)には京都より除目を知らせる飛脚が鎌倉に到着し、頼朝が征夷大将軍に叙せられたことを報じます。名実ともに鎌倉幕府が成立したわけです。
建久四年(一一九三年)五月に頼朝は御家人たちを集めて富士の裾野で大規模な巻狩を執り行います。これは平時にあって、とかく緩みがちな御家人たちへの統制に喝を入れるための軍事演習だったと云われています。この一大セレモニーの最中、曽我物語で知られる曾我兄弟の仇討ちという大事件も発生しました。
この年の七月十八日、『吾妻鏡』には頼朝が小坪へ遊行に出掛けた事が記されます。長江、大多和の武者たちが小坪の潟に仮屋を設け酒や料理で頼朝をもてなし、弓術の余興も行われ、頼朝は「事ごとに感に入られ、興に乗り秋の日の娯楽を尽くし、黄昏になって帰られたという」とあります。奥州合戦、上洛、富士の巻狩と続いた大事を乗り切ってホッとしたところで、よい骨休めになったことでしょう。当時の小坪は鎌倉武将たちにとって、格好の遊び場と認識されていたようです。
頼朝は正治元年(一一九九年)に没し、嫡男の頼家が二代将軍に任じられました。頼家が生まれた寿永元年(一一八二年)は、父頼朝が愛妾亀前を小坪に囲ってひと騒動あった年ですが、それから十八年後の正治二年(一二〇〇年)、数えで十九歳となった頼家は、御家人を率いて小坪の海岸で遊んだと『吾妻鏡』に記されます。当時小坪に館を構える小坂太郎(光頼)と長江四郎(明義)らが酒宴を提供しました。現在小坪漁港で魚屋を営む「谷亀」さんの裏手が小坂館跡といわれ、館中にあったといわれる「殿の井」と呼ばれる井戸が現存します。長江氏は頼朝の小坪遊行のときにも接待役として名前が出てきました。現在の葉山町「長柄」が長江氏ゆかりの地だと思われますが、当時は逗子一帯までも勢力下にあったのでしょう。

小坪海岸で催された笠懸には、結城七郎朝光、小笠原阿波弥太郎、海野小太郎幸氏、市河四郎義胤、和田兵衞尉常盛らが射手になったと伝えられます。また、船に乗って酒盛りしていたところ、朝夷名三郎義秀が頼家から「お前は泳ぎが上手いらしいじゃないか、見せてみよ」と命じられて海に入り、素潜りで鮫を三匹仕留めて見せました。これに感心した頼家は自分の乗っていた名馬を褒美として義秀に与えたとあります。今日、逗子海岸で十一月に開催される流鏑馬は、頼家が催した小坪笠懸の故事にちなんだものです。