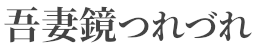小坪漁港から披露山へ向かう狭い坂道の途中にある「殿の井」は、「将軍たちを愉しませた小坪海岸」でも紹介したように、土地の人から親しみを込めて「とんのい」と呼ばれています。この井戸に向かって左手の民家裏にひっそり佇む小坂天王社という神社は、鎌倉時代にこの土地に住んだ武将、小坂太郎光頼の居館跡とされ、小坂殿の屋敷内にあったので殿の井と呼ばれるようになりました。かつて小坪は鎌倉四囲(東西南北)の内と見なされましたから、殿と言えば鎌倉殿を指すわけですが、小坪の衆にはもうひとりの殿がいたのです。

小坂光頼は二代将軍源頼家を小坪に招き、長江明義らと酒肴を整え手厚くもてなした御家人のひとりです。「相模武士 鎌倉党」(湯山学著)によれば長江明義は桓武平氏鎌倉党の一族で、現在の葉山町長柄の地を本領とし、葉山一帯を支配しました。長江氏は鎌倉党でありながら、領地は三浦に近く、叔母が三浦党杉本義宗に嫁した縁などから、源頼朝が挙兵直後に惨敗した石橋山合戦では、鎌倉党がこぞって参戦した平家方の大庭軍には加わらず、三浦党の一味として衣笠城に籠もり平家方と戦いました。
このように当時の三浦党は現在の逗子、葉山あたりまで勢力を伸ばしていましたから、小坪に館を構えた小坂氏も三浦党の武将だろうと思って調べてみると、小坂の名字を持つ人物は三浦一族に見当たりません。『吾妻鏡』正治二年九月の注には、小坂光頼について「生没年未詳。時田義遠の男」との記述があり、さらに時田義遠の出自をたどると、相模国からはるか遠方、信濃源氏の武将だったと判明しました。どうした縁で光頼は小坪の地へやって来たのか、大いに気になります。
清和源氏と称される武門源氏は清和天皇の皇子、貞純親王(陽成天皇の皇子、元平親王とも)の子息経基が「源」の氏姓を賜り臣籍に下ったのが始祖とされます。経基の孫に当たる頼信は河内源氏の祖となり、嫡子頼義の子孫は鎌倉幕府を拓いた頼朝へ続きますが、頼義の弟頼季は京武者から信濃国へ転じて高井郡井上郷(現在の長野県須坂市鮎川南部)に入植し、井上太郎を名乗ります。頼季が彼の地へ土着した動機について、宮下玄覇氏は著作「信濃源氏」の中で、良質の馬を産出する牧の存在を指摘します。当時の戦闘形態は馬に乗り弓を射る騎射が中心でしたから、優駿を確保するのは武将にとって何よりの重要事。武門源氏の一員として、頼季は牧の経営に乗り出したのでしょう。『平家物語』「知章最期」の段に、一ノ谷の合戦に敗れた平知盛は信濃国井上産究竟の名馬「井上黒」に乗ったお陰で命拾いしたという逸話があります。
頼季の嫡子満実は信濃国に住み井上三郎太郎を称したと尊卑分脈に記され、その子孫に時田、矢井守、高梨、芳美、須田など、井上郷周辺の地を領した庶流が生まれたとされます(前掲「信濃源氏」より)。満実の子息光平が時田太郎を名乗り、その末裔が時田義遠と考えられます。小坂光頼の「光」は時田光平から一字をもらったのでしょう。信濃源氏井上氏の庶流時田氏を父に持つ光頼が小坂を名字とした理由は定かではありませんが、須坂市に残る井上氏居館跡のすぐ南方に、十世紀の延喜式に載せられた小坂神社(下記地図)が現存し、井上氏が近くに住んだ十一世紀後半、源氏の氏神である八幡宮を祀ったと由緒にあります。光頼は信濃を離れ小坪へ移住する際、故郷の地名にちなむ小坂を名乗ったのか、あるいは時田氏は代々小坂神社を護る職にあったとも考えられます。ちなみに、小坪の小坂天王社の近くにも、おそらく光頼が勧請した八幡宮が現存します。
(公開日:2025-08-06)