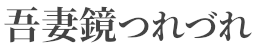小坂光頼と小坪を結びつける鍵となった、頼家と信濃武士との関係が見えてきました。頼家は舅である能員の地位や人脈を利用して、幕府重臣たちとは関係の薄い信濃出身者を側近に登用したのです。そうした流れの中で、小坂光頼もまた鎌倉へ出仕して頼家の側に仕えるひとりに推挙されたと考えられます。
建仁二年(一二〇二年)九月に頼家が数百騎の武者を引き連れ伊豆、駿河両国へ狩りに出掛けた際、射手に選ばれた十人の勇者に小坂弥三郎の名があります。『吾妻鏡』の注には「小坂光頼の男三郎政義、あるいは政義の男小三郎長頼」とありますから、光頼は家族を伴って小坪へ移住し、少なくとも孫の代まで暮らしたと思われます。他の武将のように本宅は領地に残したまま、出先機関として鎌倉に宿所を設けたわけではなく、小坪に骨を埋める覚悟で信濃国を後にしたのです。
ところで小坂氏とは、小坪の衆にとってどのような殿さまだったのでしょうか。二代将軍頼家の時代は、頼朝が鎌倉に入部しておよそ二十年の歳月が流れ、武士、商人、職人、僧侶、芸能者など多様な人々が集う興隆著しい都市となり、とりわけ大町四辻一帯は町屋と呼ばれる商売小屋が建ち並ぶ賑やかな市場でした。少し後の時代になりますが、建長三年(一二五一年)に幕府は増えすぎた商売人の活動を規制するため、彼らの活動場所を大町、小町、米町、亀ヶ谷辻、和賀江、大蔵辻、気和飛坂山上の七個所に制限します。
このうちの大町は現在の大町四ツ角(地図)、小町は本覚寺の風神雷神像の構える門前の夷堂橋あたり、米町は大町四ツ角から若宮大路へ向かい下馬の手前に掛かる延命寺橋付近(地図)で、ここは現在も米町の地名が残ります。また、大町四ツ角から南に坂を下ったところを流れる逆川に掛かる橋は魚町橋と呼びますから、かつてここに魚を商う町屋があったと推定できます。つまり夷堂橋、魚町橋、延命寺橋に囲まれた大町三角地帯は鎌倉でも有数の商業地だったのです。小町に商売の神とされる恵比寿様を祀ったお堂があるのも納得いきます。小坪の漁師たちは、採れた魚貝を魚町へ運んで売りさばき、鎌倉に暮らす人々の胃袋を満たしたことでしょう。

大町三角地帯は多くの商売人たちがこぞって出店を願う一等地ゆえに場所取り合戦は凄まじいものだったに違いありません。当時、一般庶民の権利や財産、生命を保護する公的な仕組みは整備されていませんから、自己救済と言って自分のものは自分で守る。それができなければ泣き寝入りするしかありません。そんな殺伐とした社会を生きる庶民にとり、頼りになるのは武家や貴族、寺社といった権門の後ろ盾です。
小坪の衆にとって小坂の殿さまは、願ってもないほど心強い味方だったはず。なにしろ将軍家と同じ清和天皇の血を引く名門の信濃源氏であり、幕府の重鎮である比企能員とも浅からぬ関係を持ちます。比企氏が居館を構える比企谷は小町の夷堂橋からすぐ目の前ですから、大町三角地帯は比企氏にとっては門前町のようなもの。その治安維持に強い影響力を持っていたに違いありません。信濃国は、今で言うところの海なし県です。そんな遠方からやって来た頼もしい殿さまに、小坪の衆は新鮮な魚貝を献上して最大限に持てなし、それと引き替えに町屋での商売に対する庇護を受ける良好な関係を築いたのでしょう。
建仁三年(一二〇三年)、頼家が病を得て危篤となったのを好機と見て、北条時政は比企一族を滅ぼし、頼家も翌年には幽閉先の伊豆で殺害され、信濃源氏はよりどころを失います。頼家の側近だった小笠原長経、中野能成、細野四郎兵衛尉は拘禁され、おそらく鎌倉から追放されたのでしょうが、小坂光頼の動向は不明です。鎌倉幕府滅亡後の小坪は美濃国土岐氏の一族、饗庭氏の所領となりました(「相模武士 鎌倉党」より)。小坂氏がいつ小坪の地を離れたのかはともかく、その館跡に祠を建て永く今日まで敬い続けるのですから、小坂殿と小坪の衆はよほど厚い信頼関係で結ばれていたと思われます。
(公開日:2025-08-08)