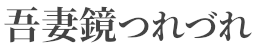鎌倉幕府の公式歴史書である『吾妻鏡』にも小坪坂の合戦について記述はありますが、三浦党が頼朝の敗戦を知って「~思いがけぬことと急ぎ帰った。その途中の由井浦で、畠山次郎重忠と数刻にわたって戦った。」とあっさり語るのみで、残念ながら小坪の地名はでてきません。
『吾妻鏡』に小坪の地名が現れるのはそれから二年後の寿永元年六月一日の条です。「武衛(源頼朝)は御寵愛の亀前という妾女を小中太(中原)光家の小窪の宅にお招きになった。」と、なにやら穏やかならざる雲行きです。「小窪」と記載されていますが、同じ光家宅を後に「小坪」とも記載しているので、二通りの字が当てられたと分かります。
ちなみに「坪」とは当時の建築様式である書院造における中庭のことで、三方を家屋で囲まれた小さな空間を指します。現在の小坪漁港は逗子マリーナ造成のため西側の岬は消滅していますが、古地図を見ると確かにここは三方を山に囲まれた「坪」だったと実感できます。

寿永二年は頼朝の正妻北条政子が第二子を身ごもった年です。頼朝と政子の間にはすでに長女(大姫)はあっても、家督を継ぐべき男児は生まれていません。伊豆国の北条館から鎌倉に移住して東国武家の棟梁としての地歩を固めつつあった頼朝は、平家との全面対決はもう少し先となる情勢のもとで、挙兵当初に比べて大いに平穏な暮らしを送っていたと思われます。
この年の初頭、政子の懐妊が明らかになると男児誕生の期待が高まり、安産を祈念して行われたのが由井浦から鶴岡八幡宮への参道(現在の段葛)の整備で、頼朝自ら指揮を執ったと『吾妻鏡』の同年三月の条に記されます。こうしたうるわしいパフォーマンスの裏で、頼朝はその年の春から御所に仕える女房であった亀前と関係を持ったのですから、隅に置けない男です。しかも密事の露呈を恐れ、臣下の家にこっそり匿うという手管を見せます。
小中太(中原)光家という人物は、頼朝が伊豆で流人生活を送っていた頃から仕える忠臣で、中原姓は文人の家系ですから、戦闘で手柄を立てるのではなく貴人の側にあって内政にあたる御家人だったと思われます。頼朝が挙兵を決意し、相模国の源氏家人へ決起に同調するよう密使を送ったときに、光家は副官に抜擢されていますから、頼朝の信が厚い家臣だったといってよいでしょう。
それが裏目に出て愛人の隠れ家に自宅を差し出す羽目になったのですから、光家にとっては大いなる迷惑だったに違いありません。政子の嫉妬心の強さは家臣の間でも知らぬ者はなく、頼朝に娘を献上するように命じられた御家人が、政子の嫉妬を恐れて、大急ぎで娘の縁談を決めてしまった、というエピソードも『吾妻鏡』には採録されています。
ところで光家の家は小坪のどのあたりに在ったのか、正確な地点を特定するのは今となってはかないませんが、可能な範囲で推測してみましょう。手がかりになる記述が『吾妻鏡』に残されています。「(光家の宅は)御浜出になる際にも便利な地であるという」。小さな漁港の小坪に砂浜はなかったはずですから、「御浜出」は由比ヶ浜を指すと思われます。現在の小坪漁港に光家宅があったとすると、浜へ出るのに便利だという記述は不自然です。頼朝の暮らす御邸(現在の鎌倉市雪ノ下3丁目)から小坪へ出るには、小坪坂を越えるか、飯島崎の先端をぐるっと回る崖沿いの道を通らなければならず、とても便利な地とはいえません。
鎌倉側から浜に出やすい地となれば、現在の小坪海岸トンネルを海側に迂回した先の「六角の井」(地図)がある住宅地あたり、小坪飯島公園プールや正覚寺がある平地です。見渡す限り相模湾が広がる絶景の地は、周囲には民家も少なく、隠れ家的な雰囲気たっぷりです。後にリゾートマンションの逗子マリーナが建設されるこの好立地は、別荘地として頼朝のお墨付きだったと言えるかも知れません。