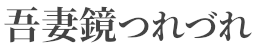頼朝が小坪に愛妾を囲った同じ年の十月、無事に若君(後の二代将軍頼家)を出産して御所へ戻ってきた政子に、頼朝の浮気が密告され事態は急転直下の展開を見せます。密告したのは政子の父時政の後妻牧御方です。政子にとっては継母に当たる牧御方にどんな思惑があったのか知れませんが、裏で時政が糸を引いていた可能性はあります。
愛妾亀前はこのとき、なぜか光家の小坪宅から、伏見冠者(藤原)広綱の飯島邸に移っていました。現在の材木座海岸に面する一帯を指す飯島という旧い地名は、国道134号線沿いの市営駐車場裏手にある「飯島バス停」や小坪海岸トンネルを抜けた先の「小坪飯島公園」などに残ります。小坪と飯島は隣接する地なので、鶴岡八幡宮に近い御所から通う便にはさしたる違いはないはず。とすれば伏見冠者という人物が頼朝の寵を得たからだと考えられます。
京都で生まれ育った頼朝は万事京風好みで、関東の武者を田舎者と見下して、京から下ってくる客人を厚くもてなしました。広綱も京都の事情に通じ、『吾妻鏡』には「文筆に秀でた右筆」とあるので、愛人と過ごす数刻の段取りや宴席の盛り上げ方などが光家より巧みだったからではないでしょうか。
そうやって愛人とよろしくやっている夫に激高した政子は、牧三郎宗親を使って飯島の伏見邸を襲撃させます。「広綱は亀前を伴ってかろうじて逃げだし、大多和五郎義久の鐙摺の宅に行った」と『吾妻鏡』は伝えます。いやはや、噂に違わず政子は気性の荒い女性だったわけです。牧三郎宗親とは、政子に告げ口をした牧御方の兄(時親)とされますから、北条一門が総力を挙げて頼朝の浮気を封じ込めようとしたのです。政子が生んだ嫡男の他に、頼朝の血を受け継ぐ男児があってはならぬという政治的意図が見え隠れします。
再び「小坪」の地名が『吾妻鏡』に登場するのは、頼朝の愛人宅が正室政子によって破壊された一カ月後の十二月です。「頼朝の御寵女(亀前)が小中太(中原)光家の小坪の宅に移り住んだ」とあり、ここでようやく現在と同じ「小坪」との表記がなされました。夫の愛人宅を襲撃させる政子も大した猛者ですが、たった一カ月で愛人を呼び戻す頼朝も負けてはいません。かわいそうなのは光家で「御台所(政子)のお怒りを頻りに恐れていたが頼朝の御寵愛が日を追って募ったため、やむなく仰せに従ったという」と『吾妻鏡』の筆者も同情を込めて付言しています。
襲撃事件後の経緯を述べておくと、事件二日後に頼朝は自ら鐙摺へ出かけ、襲撃犯の牧三郎宗親と被害者の伏見冠者広綱を呼び出して経緯を尋問します。鐙摺とは現在の葉山マリーナ近くの旗立山(地図)のことで、有名な料亭日影茶屋の向かいの小山が鐙摺城跡とされます。そこで頼朝は、政子の命に逆らえないのは仕方ないとしても、なぜ事前に知らせて来なかったんだとむちゃくちゃな理屈で詰問し、宗親の髻を切って恥辱を与えたそうです。

当時の成人男子は髻を結った上に烏帽子を被るのが作法で、相手の烏帽子をはたき落とすだけで刃傷沙汰に発展しかねない無礼な振る舞い。まして髻を切るなどは最上級の恥辱となります。宗親は「泣いて逃亡した」そうです。一方、愛人を匿っていた広綱も無傷ではいられず、政子の圧力によって遠江国へ配流されました。二人とも、詰まらぬ事で人生を誤ったものです。
その後、亀前がどのような人生を送ったのかは不明です。しばらく小坪の宅で過ごした後、頼朝の寵がさめた頃には、いずこかの武士の妻に収まって鎌倉を去ったのでしょう。折々に小坪の宅を懐かしく思い起こしたでしょうか。
(公開日:2025-08-02)