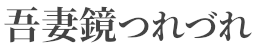『吾妻鏡』は平清盛政権の転覆を謀るクーデター計画の密談場面で幕を開けます。場所は平安京の三条大路北と東洞院大路の交わるあたり。現在は地下鉄烏丸線の烏丸御池駅からすぐ東側、中京郵便局の敷地に「平安京東洞院大路・曇華院史跡」の案内板が立ち、少し北へ向かうと「高倉宮跡」の石碑があります。

この三条高倉の御所に住まう後白河法皇の第二皇子(第三皇子とも)以仁王を密かに訪ねたのは、摂津源氏の棟梁にして武門源氏としては破格の三位に叙勲された源頼政とその嫡男仲綱です。平清盛の血を引く安徳天皇の即位により皇位継承の夢を絶たれて失意に沈む以仁王と、栄華を極める平家をはた目に平々凡々とした宮仕えに明け暮れ老齢を迎えた頼政は、暴君として悪政をふるう清盛を滅ぼし、鬱々とした自身の生涯を一発逆転する大事業に乗り出した、とするのが吾妻鏡が描く源平争乱の発端です。まさに高倉御所は鎌倉幕府誕生の原点と呼ぶべき場所なのです。
清盛打倒クーデターの首謀者は、吾妻鏡の記述に従えば義憤に燃える頼政となりますが、それは吾妻鏡編者の曲筆で、真の首謀者は皇位奪取を渇望する以仁王だったとする研究者もあります。なお、本サイトでは頼政、以仁王のいずれでもない第三の人物が主導したのだと主張します。詳しくは『深読み吾妻鏡』を参照ください。
頼政と鵺退治の伝説
以仁王を唆してクーデターを首謀したのか、それとも王家の皇位継承争いに引っ張り込まれ、やむなく反乱軍に加わったのかはともかく、頼政という人物は鎌倉幕府の成立に決定的な役割を果たしたことは間違いありません。その人物像を垣間見るエピソードは『平家物語』にいくつか収録されていますが、中でも有名なものは「鵺」の段でしょう。
内裏(皇居)を中心として所管省を集約した国政の中核空間である大内裏を警護する大内守護だった頼政は、近衛天皇の御代、夜な夜な御殿の上に現れ主上をおびえ悩ます妖怪変化の退治を命じられます。謀叛人の討伐なら職責なれど、姿形のない化け物を討つなどできるだろうかとひるみますが、勅諚ならば仕方がない腹を括り、重籐の弓に矢を二本たずさえて南殿の大床に伺候します。そして現れた変化の物を見事射落としてみれば、頭は猿、胴体は狸、手足は虎の姿で、鳴き声は鵺に似ていたと言います。
この時頼政が退治した鵺を祀った鵺大明神と、鏃を洗ったとされる鵺池は、現在の二条城に北接する二条公園にあります。ここは平安京では内裏南側の宮内省あたりで、鵺は東三条つまり南東側から飛翔してきたことになります。

武人としての面目躍如させた頼政は、天皇の御感に与り師子王という御剣を下賜されます。御剣を授け渡す役を務めた左大臣藤原道長が「ほとゝぎす名をも雲井にあぐるかな」と歌いかけて武功を賞賛すると、頼政は即座に「弓はり月のいるにまかせて」(偶然ですと謙遜した意)と下の句を返し、天皇も道長も大いに感心したと言います。頼政は武芸にとどまらず歌道にも優れた粋な都人だったのです。
近衛河原の家に火を放つ
頼政の仕組んだクーデター計画は、高倉御所での密会からひと月余り後に清盛の漏れ知るところとなり、検非違使が以仁王の身柄を拘束するため三条高倉の御所へ押しかけます。この動きを察知した頼政より、危険が迫ることを急報された以仁王は、間一髪で脱出に成功します。御所に派遣された検非違使のひとりは頼政の養子兼綱でした。この時点で、頼政が首謀者だと気付かれていなかったのです。長く平家政権とうまく折り合いをつけて生涯を送り、二年前には清盛の推挙で念願の三位昇進を果たした頼政は、重い病を得て出家した身でした。その頼政がまさか、という思いは平家側にあったでしょう。
以仁王は近江国の三井寺(園城寺)に逃れて徹底抗戦の構えを見せ、延暦寺や南都の興福寺にも挙兵を促します。この噂が京に広まると、頼政はすでに言い逃れはできぬと覚悟し、近衛河原の自邸に火を放ち一族を引き連れて三井寺へ向かいます。「近衛大路の南、河原の東」(『山塊記』五月二十二日条)にあったとされる頼政邸は、現在の近衛通に南接する京都大学薬学部あたりでしょうか。これといった石碑や案内板はありません。

近衛大路は大内裏の陽明門に到り、門をくぐれば左衛門府、その先はすぐ内裏に通じます。大内守護を長く務めた頼政は職住接近した好立地に家を持っていました。後述するように、頼朝を輩出した河内源氏の拠点が下京の六条にあったことを思えば、頼政はより上流の階級に属したと言えるでしょう。武者でありながら歌人として歌集を出すほどの教養人だった頼政は、貴族たちの催す歌会にたびたび出席するなど、都人との交流を保った人ですから、貴族たちの多く住む上京に近い住居は必然だったわけです。一方、受領として地方への勢力扶植に励む河内源氏は東国の居館が生活基盤で、時に応じて上洛する生活様式でしたから、下京の五条大路以南に宿所を持っても不自由なかったのでしょう。
以仁王、頼政が散った終焉の地
三井寺に籠城した反乱分子に対し、平家政権は性急な武力行使は控え、謀叛人を引き渡すよう大衆(貴族出身ではない衆徒)を説得します。これが奏功し三井寺の以仁王を支援する勢力に分断が生じ、さらに延暦寺の大衆も平家支持へ傾くに及び、以仁王と頼政は南都興福寺への脱出に一縷(る)の望みをかけ、闇夜を突いて出奔します。この動きをつかんだ平家は追討軍を派遣します。時間稼ぎのため宇治川で合戦を挑んだ頼政はついに切腹、木津川に沿って南へ逃れる以仁王も、光明山の鳥居前で追討使に追い付かれ最期を遂げました。
多くの修学旅行生が訪れる宇治平等院(地図)には、頼政が腹を切ったとされる『扇之芝』と『源三位頼政公墓所』があります。


以仁王終焉の地である木津川市山城町綺田には以仁王を祀る高倉神社(地図)と宮内庁の管理する墓所があります。