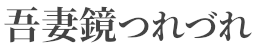大庭御厨は鎌倉一帯を開発した鎌倉権五郎景正が、相模国高座郡大庭郷の領地を伊勢神宮(内宮)に寄進して成立した荘園です。伊勢神宮の神官(禰宜)にして大庭御厨の領家だった荒木田氏は、鵠沼郷内の伊介神社(現、皇大神社)に居住し、ここを御厨の運営に当たる
景正の後裔、大庭景親が支配した大庭御厨は、東は俣野河(現、境川)から西は寒川神社領との境界まで、現在の藤沢市と茅ヶ崎市がすっぽり収まる広大な領域を占めました。景親の居城(大庭城)を中心に東は弟の俣野五郎景久の所領(現、横浜市戸塚区俣野町)、西に兄の大庭景義の所領である懐島(現、茅ヶ崎市円蔵)と、一族で荘園を分割統治しました。
鶴岡八幡宮を建て替えた際、御神体を仮殿に遷す儀式に大庭御厨の神館から
鵠沼皇大神社へは、海沿いの国道134号から引地川に沿って北上し、JR東海道線を越えてすぐです。参道に三つの鳥居を構える広い敷地で、さすが古い由緒を持つ神社だけあると思わせます。駐車場あり。
(公開日:2024-01-30)